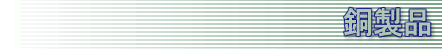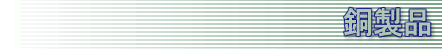中国に仏教信仰が広がり始めた頃の鍍金仏は、わずかに一・二例が知られているだけであるが、その顔つきや着衣の様はガンダーラ直系の造形を示す。それに続いて恐らく4〜5世紀初頭にかけて、逆に稚拙とも言うべき仏坐像が出現する。中国の北部は北辺の諸族が南下して占め、やがて北魏が統一を果たすことになるが、その頃北地で製作されたものと考えられている。本来は台座の裏面に柄があるので光背を有した。一般に「古式金銅仏」と通称されている。台座の前面に彫り出されているのは守護の獅子を前から捉えた姿で、衣紋や頭髪とともに鋳上がった後で刻出されている。型に彫るのと違って、小さく・固い金属面を刻むために目鼻が顔面に対して大きくやや粗い彫りになるが、それが独特の表情となってあらわれる。
小型で簡略な形姿から、移動生活を営む遊牧民の家族的・個人的な信仰対象であったと推測される。西安や洛陽といった歴代の仏教中心地において、北魏時代以前に遡る造像遺例がほとんど知られていない今日、当時の仏教交流の実態を探る上でこの北辺の金銅仏のもつ意義は極めて重要。
参照 : DK-168 |